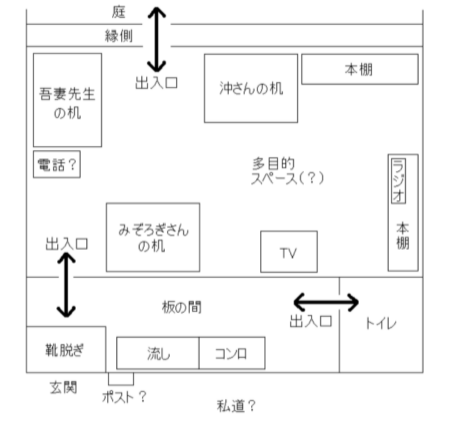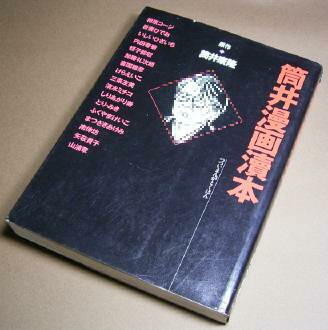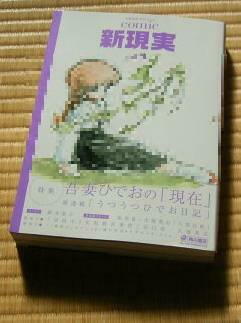(1)嘘みたいな始まり
(2006.7.17.付記:沖さんご本人と連絡がつき、このカテゴリの公開についてお許しを戴くことができました。またご教示賜ったいくつかの箇所を訂正。誤解や記憶の誤りがまだ他にもあるかと思われますが、とりあえず公開を継続。)
((2006.6.1.付記) 自分の思い出を語るにしても、そこに他人様が登場する場合、しかもその他人様のほうに重点が置かれているとなると、どこまでがネット上に公開しても良い話なのやら、なかなか判断が難しいようです。加えて、記憶を頼りに書くものというのは記述内容の正確さにどうしても限界が伴いがち。そうした点を悩んだ挙句、このカテゴリは一時公開中止していたのですが、できるだけ注意深く校閲しながら、少しづつ再開してみることにしました。)
……吾妻ひでお先生に直接お会いしてみたい、というのは念願でしたけれど、一介のファンに過ぎない自分にそんな機会があろうはずも無く、あきらめていました。それが、1975年だったかと思うのですが、ありえないような偶然で夢の実現をみることになったのです。
当時まだ高校生だった僕は趣味でプラモデルを作っており、その専門店へ足しげく通っていました。或る日、そのひどく小さな店へ行ってみると、ほぼ同年代であろう先客が1人あって、店主がその人を紹介してくれたのでした(今どきだとこういう事はあまり無いかも知れないですけれど、当時はそんな形での他人との出会いがまだ世の中に存在したんですね)。で、紹介を聞いて僕はびっくりしました。その人はマンガ家のアシスタントをしているセミプロで、それも、なんと吾妻ひでお先生に師事しておられるというのです。そしてその時に知り合ったやや長髪の人物が、後にプロデビューなさる沖由佳雄さんだったのでした。
この日、どんな会話をしたのか覚えていないのですが、多くのマンガ好きがそうであろうように、僕も自分でマンガのようなものを少し描いており、かなうなら将来マンガ家になりたいと夢見ていました。つまり沖さんと僕には3つの共通点があったのです。第一に吾妻ファン、第二に模型ファン、第三にマンガ家志望である……。だからでしょうか、何だか話がとんとん拍子に展開し、吾妻先生に会わせて頂けることになったのでした。

(この、下手な作り話のごとき出来事の舞台となった模型屋は、残念ながら店をたたんでしまって今は存在しません。画像は、かつて店があった場所です。)